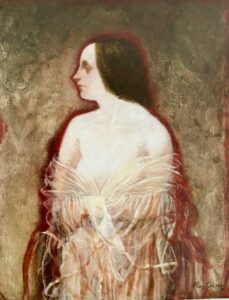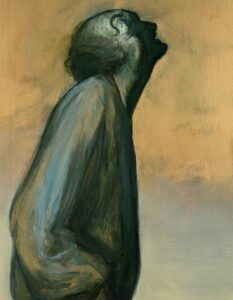最近立て続けにアンソニー・ホプキンスの映画を3本観る機会があった。
好奇心のまま映画をチョイスすると、偶然にその中で主演を演じていた。なつかしい。
現在83歳になられても、2020年「ファーザー」で認知症の父親役を演じ、アカデミー主演男優賞を取った。イギリスに居たご本人は受賞の知らせに驚いたとか。制作はイギリスとフランスの合作。両国の色合いが出ていたと感じる。介護は世界共通のテーマだ。システムや家族関係の違いから、日本の介護の共通点と相違点を考えさせられた。
二本目は1993年「日の名残り」。イギリスの名士が住む邸宅に長年仕える執事(バトラー)と女中頭との関係を全編丁寧に描いている。原作はノーベル賞作家のカズオ・イシグロだ。これを観ると「イシグロはほぼイギリス人ではないか」と思ってしまう。
三本目「チャーリング・クロス84番地」。これは原作書名で、副題に「本を愛する人のための本」とある。朝日新聞の書籍紹介記事からすぐに読みたくなった。1970年に出版された実話。ロンドンの古本屋とニューヨークに住む女性脚本家との20年にわたる往復書簡集だ。
アマゾンで検索すると、1986年に映画化されている。アンソニー・パーキンスとアン・バンクロフトが出演。ミセスロビンソンもなつかしい。映画監督である夫がアンの希望で制作したそうだ。カメラのレンズに向かってアンが語りかける多くの場面を思い出した。本作は今から35年前の作品。
控えめな店主役のアンソニーの演技に共感した。隠れた名作に出会え、ラッキーな日だった。