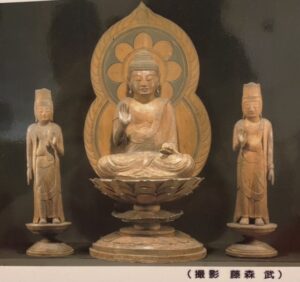東京都美術館にて2月10日から開催されているオランダ絵画展。久しぶりの上野駅。公園口の道路はすっきり整備され、駅舎は焦げ茶色の格子にカバーされて和風になった。

画中画の天使を加筆(修復後)
今回フェルメール「窓辺で手紙を読む女」の修復された絵画が話題。今回の修復により、大きな天使像の画中画が現れ、輝度も以前より全体に明るくなっている。老眼に嬉しい。
会場ではガブリエル・メツーの「レースを編む女」が印象に残った。今年冬購入したハーフコートと似たデザインなのが目を惹いた。

ガブリエル・メツー
帰宅して彼の作品を調べるとユーチューブの動画があった。しかも70点と多くの作品コレクションがあり、17世紀のオランダのファッション、食べ物、文化を楽しむことができた。38歳と若くして世を去っている。
フェルメールの作品はメツーよりずっと少なく、30数点が残されている。11人の子供を抱えて、無名のうちに生涯を閉じた。今回の作品の他に「真珠の耳飾りの少女」「牛乳を注ぐ女」などが有名だ。ミステリアスな女性と光と独特な色彩が記憶に残る。

「牛乳を注ぐミッフィ」