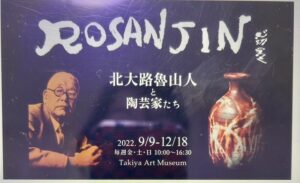2日目の朝、国宝の犬山城に行くことを決めた。
名古屋駅から名鉄線の特急ミュースカイに乗車し、約25分で犬山駅に到着だ。駅からの道は碁盤の目のようでわかりやすく、ブラブラ歩いて10分もかからない所に城下町通りが続いていた。

通りは多くの若者が点在するファストフード店近くで集まり、休日を楽しんでいる。コロナ前の賑やかさが戻ってきているそうだ。私はうなぎの寝床の町屋、旧磯部家住宅を見学した。ランチタイムでは、守口大根の奈良漬専門店の精進料理を頂く。


犬山城は木曽川の近くに築城されており、急な4階まである狭く急な階段は十分に昇る価値があった。この階段は1580年代に建設され、現存する天守の中で最も古いそうだ。
天守閣の廊下をぐるりと一周して眺める景観は貴重だ。動画に全景を収めた。悠々と流れる薄いグリーン色の木曽川が美しい。昔、高山へ行った時の車窓からの木曽川のエメラルドグリーンの水を見て感激したことを思い出した。

ゴボウも美味