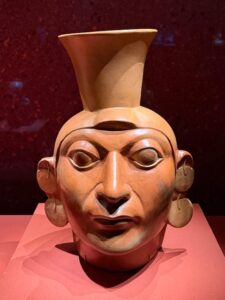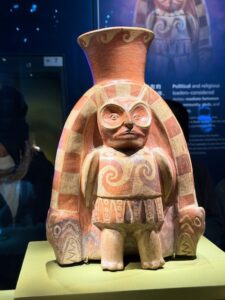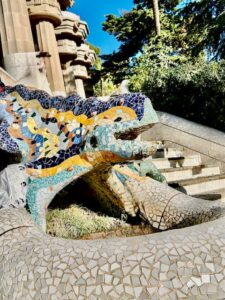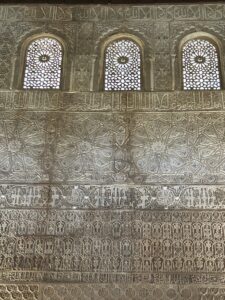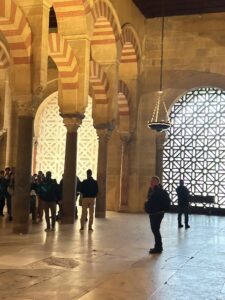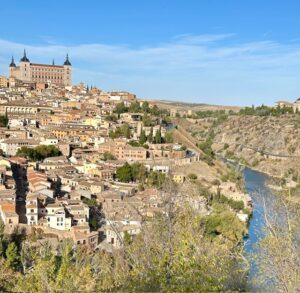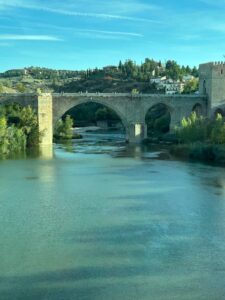明けましておめでとうございます。
新しい年、大事なく日常が流れますようご祈念いたします。
大晦日に「富山きときと空港」に飛び、昨年の気分をリセットすべく、魚津市の金太郎温泉で過ごした。


「寿司の富山」で売り出し中、アイデアは流石だ。


ホテルでは初詣のために魚津神社まで送迎バスを出す。10時30分発に予約した。第2便のせいか、利用者は4名だった。
魚津神社は能登半島地震で大きく被害を受けた。今も石の鳥居が解体されたままで、係りの方が義損金の御協賛を集めていた。
お詣りの帰り、蜃気楼が見える海岸線や山の湧水が出ている水道、大正時代の米騒動の起点となった米倉などミニ観光をした。人口4万人の魚津市のホテルのスタッフは皆親切だ。
2日の出発の朝、夜のうちにまとまった降雪があり、白色の町に変わった。9時にホテルを後にして富山駅に向かった。路面電車に乗り、ガラス美術館を訪ねた。隈研吾のスペースを広く使った贅沢な建造物だった。地元の受験生の学習コーナーもガラス越しに見える。
空港に行くまで2時間あった。美術館近くにある富山市民がお詣りに行く日枝神社を訪ね、雪舞降る中、2度目のお詣りを果たした。


空港では名物のブラックラーメンと握り寿司のセットを頂いた。大晦日は、富山駅近くの富山湾食堂の新鮮な握り寿司を食し、お寿司の富山を2回体験できた。