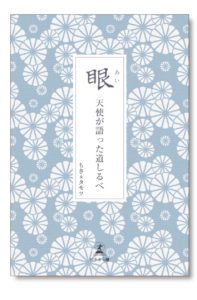2019年製作のヤン・コマサ監督のポーランド映画を観た。
小さな農村を舞台に仮釈放中の青年ダニエルと村の老司祭、少年院の司祭トマス、村人たちが登場する。実話をもとに書かれたという。
村は少し昔の時代と思われる様相だが、教会で信者から告解を受ける時、スマホで「告解の手引き」を検索して、にわか司祭のダニエルは窮地を逃れる。村で7名が死亡した交通事故の状況証拠がメール動画に残っているなど、所々で現代を感じる。
多くの語りどころがあり、もう一度観て確かめたい。物語の展開、シーンの移り変わりが早い。監督が若く、観る方の私がシニアだからかもしれない。
シニアながらに印象に残ることは、「死に対して尊厳を感じる」主人公だ。
「少年時代、喧嘩で病院に入った相手が死んだ」、という過去を持つ。出所してすぐに酒、タバコ、歓楽に溺れるが、縁あってある村で病を持つ老司祭の代理の仕事につく。
司祭は村の冠婚葬祭に重要な役がある。いつも冷徹な目をしているダニエルの眼光が優しく変わるのは、村人の死に接する時だ。臨終のベッドに横たわる老女の手を取って「あなたは死なない」と話しかける。献花台の前で交通事故で若者を亡くした遺族たちを真剣な祈りで慰さめ、またやり場のない彼らの感情を発散させるよう導く。保留されていた事故加害者の葬儀も実現させた。
少年院でダニエルが敬愛していたトマス司祭はどういう人物だろうか、と考えた。村人や子供たちはダニエルに感謝の言葉を形にした品々を贈った。トマス司祭がそれらをじっと見つめているシーンから何か良き方向を感じたのだが。。。






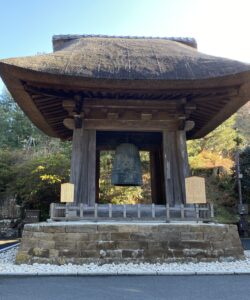
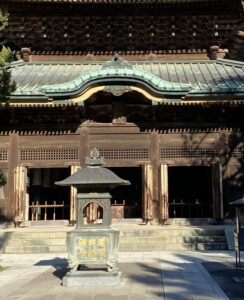
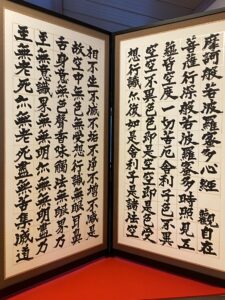
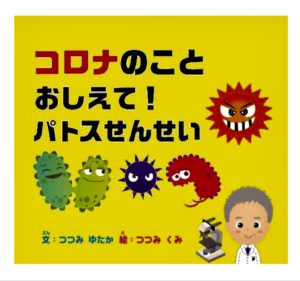 1月7日に去年4月以来、2回目の緊急事態が菅総理より宣言された。
1月7日に去年4月以来、2回目の緊急事態が菅総理より宣言された。