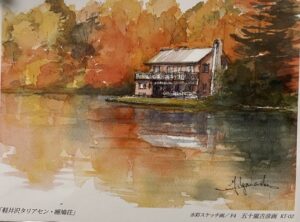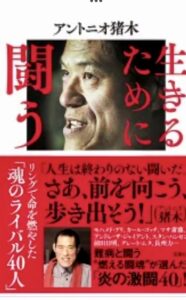年季の入った築50年のマンションに住み始めて約15年。
管理会社を持たない、入居者主体の自主管理の形態だ。
今年の大きな計画の大規模修繕工事、8月22日から始まり、11月21日に修理やお化粧直しが無事終了した。

朝10時、理事会の役員4名と施工会社責任者が集まった。建物全体の補修状態の確認で屋上から駐車場まで見廻りを1時間ほどかけて行った。
近年他の水道関係や床工事等を優先した。そのため後回しになっていた18年振りの大規模修繕工事がやっと終わり、清々しい気分だ。
政府の住宅金融支援機構から総工事費用を借り入れして実現できた。低金利で返済期間は10年間と会計にやさしい制度がある。お世話になり有難うございます。入居者の総意です。